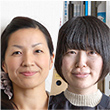マネジメント世代のキャリア選択をひらく、
成長する自己のつくり方
「人生100年時代」という概念が広まり、私たちの働き方や生き方は、より柔軟で多様なものへと変化しています。こうした変化を背景に、複数の分野や雇用形態を同時並行する「マルチキャリア」や、定年後や転職後に新たな分野で活動する「セカンドキャリア」に挑戦する人が増えています。一方で、ひとつの職種で経験や実績を積み管理職として活躍する人や、専門性を高めてきた人であるほど、別の選択肢を持つ難しさを感じて、「自分にも、新しい可能性がひらけるのだろうか」と将来に不安を抱くことがあるかもしれません。
そこで今回のダイアログは、生涯にわたって新たなキャリアの可能性を広げ、自己成長を継続するための考え方や行動とはどのようなものか、その実践的な道筋について考えます。
対話したのは、創業70周年アンバサダーで柔道家の野村忠宏さんと、所属プロゴルファーの宮里優作さんです。アスリートの世界でトップを極めたお二人が、これまでを振り返りつつ、なおも新たな道へとチャレンジを続ける現在と今後の展望を語り合いました。大和ハウス工業創業70周年特別企画の第2弾としてお届けします。
- ※本稿は2025年7月8日取材時点の内容です。
CONTRIBUTORS
今回、対話するのは・・・


新たな柔道との関わりを目指し事業創造に挑戦中
野村 忠宏
柔道家
株式会社Nextend代表取締役
大和ハウス工業 創業70周年アンバサダー(ハート大使)
柔道男子60kg級でアトランタ、シドニー、アテネで柔道史上初、また全競技を通じてアジア人初となるオリンピック3連覇を達成。2013年に弘前大学大学院で医学博士号を取得。
2015年に40歳で現役引退後は、自身がプロデュースする柔道教室「Daiwa House presents 野村道場」を開催する等、国内外にて柔道の普及活動を展開。スポーツキャスターやコメンテーターとしても活動する他、2025年1月からは目黒区青葉台に鍼灸接骨院とピラティススタジオを併設したコンディショニングラボ「Nom-Lab.(ノムラボ)」を設立し、ウェルネス事業にも取り組む経営者としても活躍している。


現役選手として若手世代と協働しゴルフ界の変革を目指す
宮里 優作
プロゴルファー /
大和ハウス工業所属
1980年、兄の聖志、妹の藍と共に、後に三兄妹全員がプロゴルファーになる宮里家の次男として沖縄県で生まれる。2013年、ツアー最終戦の「ゴルフ日本シリーズJTカップ」で、プロ転向11年目にして、今も語り継がれる、感動的な国内ツアー初優勝を手にした。その後、2016年から2年間、日本ゴルフツアー機構(JGTO)選手会長に就任、ファンとの距離を縮める改革を重点に置き、精力的に活動。2017年には年間4勝を挙げ、史上初の選手会長就任中に賞金王に輝く。2024年6月より大和ハウス工業と所属契約を締結。
これまで築いてきたキャリアを生かしながら、多様なキャリアの選択肢をつくるための考え方や行動には、どのようなものがあるでしょうか。野村さんと宮里さんの実践と経験を通じて、一緒に考えてみましょう。
1
年齢と経験で変化する
セルフマネジメントと自己理解


-

宮里さんは、プロを意識したり、高いレベルを目指し始めたのは何歳頃からですか。
-

中学生の頃から、日本ジュニアゴルフ選手権で、ある程度の活躍をしていました。歴代のジュニア優勝者を見ると、後にプロになった方ばかりで、それでプロになろうと思い、ゴルフ部がある高校を選びました。
学生時代にはプロの試合にも出場して、自分のレベルを把握できるようになりました。ようやく「やれるんじゃないか」という手応えを感じるようになったのは、大学生の中頃だったと思います。
-

世界が見えてくると、意識が変わっていきますよね。技術のうまさや強さ、セルフマネジメント、コンディショニングなど、いろいろと極めたいものがあったと思います。何を意識していましたか?
-

若い頃は、誰もやっていないことをやりたいという気持ちが常にありました。セルフマネジメントとは、発見していくことでもあるので、まずは試して、これは取り入れる、これは要らないという判断を繰り返しながら、常にゴルフにプラスになることを探していました。
ゴルフ以外でも、日常でテレビを見ていて「これはゴルフにも共通しているのかな」と何か結び付けられないか考える。常に頭の中にゴルフがある感じで生活していましたし、今も続いています。


-

今は睡眠や栄養、フィジカルやメンタルのケアなど、さまざまな情報があふれている。でも、私たちの若い頃、20~30年前は、自分のコンディショニングについての情報がまだそれほどなかったですよね。
-

なかったです。人に聞くか、自分で実践して確かめるかの手探り状態でした。
野村さんは、オリンピックで活躍してこられました。4年に1度というスパンに合わせて、良い波を持ってくるような、セルフマネジメントやさまざまな調整方法があったのではと思います。
-

そうですね。4年というと、年齢とともに、心身にさまざまな変化が起こります。自分の4年後の変化をしっかりと見極めながら、やるべきことを逆算して、取り組んでいましたね。
若い頃は、宮里さんと同じように、今の自分に必要なものかどうかの取捨選択だけはしっかりやっていたように思います。年齢を重ねると、けがが増えたり、回復が遅くなったりするので、体のメンテナンスにより気を遣うようにもなりました。
-

時間がかかるようになりますよね。年齢とともに、ウォームアップの方法が変わってきますし、勉強すればするほど、やらなければいけないことが増えている気がします。
-

情報量も知識も増えて、技術も向上し、準備の仕方も含めてアスリートとして伸びている部分と、コントロールしきれないフィジカルの衰えとの乖離(かいり)がありますね。歯がゆい時もありますね。


-

打てていたショットが打てなくなる、できていたスイングができなくなる、というように、今までできていたことができなくなって、ゼロからまたやり直し、となると手間がかかります。
ゴルフは道具を使いますし、道具は日々進化しているので、その影響を研究する必要もあります。やることがたくさんあるので、休む時間をつくらないと、頭に入ってこない時があります。ゴルフを一度忘れるような時間もちゃんとつくるように、諸先輩方から言われていたので、今も実践しています。
-

そこは結構大事ですね。息抜きやリラックスする時間をつくる。
-

昔はよく、体力づくりの一環で、ゴルファーで野球チームをつくって、オフは野球をしていました。野球選手はオフにゴルフをする(笑)。今は、何か別のことやると逆に支障がでそうだからやめておこう、とか考えるようにもなっていますが。
-

アスリートは皆そうだと思いますが、俯瞰的に、客観的に自分を見て、良いところも駄目なところも含めて自己理解する能力が高いような気がします。それができない人は、スポーツの世界で上まで行けないし、良い状態を長く、長いスパンで戦い続けることはできませんよね。
-

そうですよね。僕の場合は、自分の状態を客観的に理解するために、自分のスイングを数値化させて、それと自分の感覚が合っているかどうかという作業を必ずやっています。
データと照らし合わせて、自分の認識とのズレを数カ月おきに埋めていく作業が重要になっています。それが今のセルフコントロール、セルフマネジメントですね。
-

自分の状態を理解するために、今でも頼りにしている人や、アドバイスをもらう人はいますか。
信頼できる人が一人いる、というだけで全然違いますよね。 -

自分の場合は、コーチが父でした。父も高齢になってきていますが、私のスイングを誰よりも近くで見てきた人なので、迷った時は父に画像を送って相談します。アドバイスが欲しいわけではないのですが、「それでいいのでは」と背中を押してくれる存在です。
セルフマネジメントも大事ですが、自分だけではどうにもならないこともあるので、相談できる人をつくった方が良いと思います。
2
次世代への貢献が自分自身のキャリアもひらく


-

私は引退して10年がたちました。引退後は、大学教員や指導者となる選択肢もあり得ましたが、柔道から離れる期間をつくり、やってみたい活動もいくつかありました。
そうやって自分のペースを大事にしながら、どのように柔道と関わり、誰に何を伝えていきたいかを改めて考えるうちに、チャンピオンを育てるよりも、子どもたちと楽しく柔道をしたいという思いが強くなっていきました。
そこで、全国の子どもたちを対象に、柔道を楽しみ、一流の技術に触れ合う機会をつくることにしました。世界を制した一流柔道家を講師に招き、「野村道場」というイベントを主催して、全国を巡っています。


2025年6月21日に開催された「Daiwa House presents 野村道場 FUN TO JUDO Vol.2」の様子。大和ハウス工業は特別協賛として参画。会場となった大和ハウスグループみらい価値共創センター「コトクリエ」には、多くの子どもたちとその家族らが集い、楽しい柔道と一流選手の迫力ある技に目を輝かせていた。
-

私は以前、選手会長を2年間務めました。選手を取りまとめる立場として、自分たちの置かれているいわば職場をこれからどう変革していくか、現場である選手の立場から何ができるかをいろいろと考え、実行していきました。
とにかく男子ゴルフをもっと知ってもらい、より多くの方々にトーナメントを見に来て、思い出を持って帰ってもらいたい、という強い思いがありました。同時に、観客が減り、試合数も減ると、若い選手が育たない環境になってしまうという危機感もありました。
そこで、選手会からトーナメント主催者に対して、「まずはSNS時代への対応として、写真と動画の撮影を解禁しましょう」と提案しました。すると、主催者側からは「選手がOKと言ってくれるならぜひ」という反応で、どうやら、それまで選手の方がNGを出すだろうと思われていたようでした。
選手会から働きかけることで、主催者とのコミュニケーションのズレが解消されました。それで選手たちに協力を呼び掛けて、試合が終わった後、観客が選手と一緒に写真を撮れるような機会をつくれるようになり、少しずつ活動が広がっていきました。
-

若い選手たちの反応はどうでしたか。
-

意外にも、若い選手の方がすごく乗り気で、「僕に何ができますか」と積極的でした。彼らは、ファンサービスが本当に素晴らしく、YouTubeをやっている選手もいて、その辺は逆に教わるくらいです。
-

若い世代には情報発信やボランタリーな活動に積極的な子が多いですよね。自分たちの世代だと、若い頃は、「結果を出せばいいでしょう、後のことは面倒だ」というような人が多かったように思います。それでも、ある程度経験を積んでいくと、自分だけではなく、業界全体へと視野が広がってきて、そのために柔道やゴルフのファンをつくらなければ、といったことに気付くようになります。


-

私たちも、小さい頃はプロの選手が好きで、トーナメントに応援に行って、プロ選手に肩をたたかれたり、握手してもらったりと、すごくうれしかったという思い出があります。逆にサインをもらいに行ったのにもらえなかったこともあって、そうしたロスを少しでも解消して、もう一回見に行きたいと思ってもらえるようにしたかったのです。
-

子どもの時にトップ選手やオリンピック金メダリストと会った記憶、「頑張れよ」と言ってもらった記憶は鮮明に残りますよね。
ちょっとした言動が、後にどうつながり、影響を与えるのかを考えながら行動しなければいけない。それがスポーツの世界で結果を出してきた人たちのひとつの大きな役割だと思います。
-

今の若い選手たちの技術力はとても高いので、もう自分には教えられることはないと思っているのですが、それでも彼らを導くことはできると思っています。
選手会長や理事としての経験を通じて、見えなかった部分が見えてきたり、やるべきことやそうでないことのすみ分けがうまくできるようになりました。
ただ、選手会長としての活動に時間を取られてしまい、練習時間がなく、なかなかプレーに集中できなくなったこともありました。勝負している時は、集中して周りが見えなくなったりもしてしまうので。それで、僕の代から選手会長の仕事を分担して負担を減らせるようにしました。マルチキャリアの工夫です。
-

自分の置かれている立場によって、考え方は変わってきます。選手じゃないとできないこともあります。引退したら組織の中での影響力はあるかもしれないけど、外に向けての影響力なら、みんなが注目するのはやっぱり現役のチャンピオンです。
今一番輝いている現役選手たちは、試合を通じて世の中に柔道を広めること。そして、引退した先輩方は、現役選手のための環境をつくり、導いてあげること。それぞれが、お互いの役割に対する共通認識を持って一緒に動かないと変わりません。
現役と引退者、組織の内部と外部、それぞれが自分の強みや持ち味を生かしながらやっていけばよいのです。思いは一緒ですから。
3
セカンドキャリアで広がる新たな挑戦と自己成長


-

セカンドキャリアをどのように歩んでいくのかについては、アスリートはもちろん、誰にとっても大きな課題ですよね。
自分が引退した時は、「よし、これをやるぞ」と思い当たるものは特になかった。でも、今までの経験から、スポーツのコメンテーターや講演の話をもらって、ひたすら求められる仕事をしっかりと自分なりに準備してやり抜いていこう、という思いでした。やらされている、という感覚では、うまくいきません。
引退後、何に出会うかがすごく大事だと思います。現役時代は、支えてくれるコーチはいるけれど、個人競技ですので、自分だけの世界で生きていたように思います。でも、社会というステージでは、知らないことを知っている人が大勢いる。そういう人たちをいかに巻き込みながら、自分が今まで築いてきた信頼や経験を融合させて何ができるのか。考え方ががらっと変わりました。
-

自分は現役ですが、解説のお仕事をいただいて、すごく光栄なことだと思っています。自分の経験を話すこともありますが、裏方として大会を盛り上げたい、ゴルフの魅力をもっと伝えたいという気持ちがあります。
これから50歳を迎えると、ゴルフはシニアの試合もあるので、引退というよりはセミリタイアみたいな形で、競技も続けつつ仕事もする未来を見ています。
ただ、最終的にはコースの設計をやりたいと考えています。ヨーロッパツアーを2年間経験して、日本のゴルフ場にないセッティングやいろんなつくり方を見させてもらいました。環境が選手を育てる部分が大きいですし、自分がデザインしたコースを評価してもらいながら、そこからまた自分も成長したいと思っています。


-

そうやっていろんな変化の中で、いろいろ悩んで考えて、大変だけど、また新しい武器をつくっていくことができますよね。
今年、50歳になったチャレンジとして、東京で鍼灸接骨院とピラティスのスタジオを併設したコンディショニングラボを設立しました。企業理念を考えて、そこで働く従業員の人たちと、どうやって共通認識を持ち、一緒に良いものをつくっていこうという意識を持ってもらうか。新しい事業を立ち上げたからこそ、また新しく悩みが出て、リーダーシップやマネジメントも必要になってくるし、すごく今、悩みながら学んでいますよ。
-

すごいですね。セカンドキャリアでも、いろんなことを悩みながら勉強していくなんて。
-

本気度が高いことが伝わると、過去に野村のことを見て応援してくれていた人たちが、「野村君がやるのであれば」と言っていろんな協力をしてくれる。アイデアをくれたり、サポートしてくれたり、応援してくれる人がいる。新しい世界で孤独を感じる時もあるけど、本当の意味での良い仲間が、周りにいるかどうかはすごく大事ですよね。
-

求められるものに対してはちゃんと応えつつ、次のチャレンジを設定していく。たぶんこれは、アスリート気質ですね。チャレンジャーですから。
-

勝てない選手は期待されないから、期待されるって、幸せなことだと思います。期待やプレッシャーを自分のエネルギーにできるかどうか。ものすごく苦しいものでもあるけれど、そこをしっかりと乗り越えた時にまた違う世界が見えてくるし、またひとつ上のステージに上がれます。
キャリアの選択肢を増やしていくには、やりたいことができるところまで、自分を高めていけばいい。もし、今やらなければいけないことが、やりたくないことであっても、どこかひとつ魅力を自分で見つけなければ、物事の魅力なんて絶対に見えてこない。それは自分で見いだしていかなければなりません。


-

自分の場合は、プロになってから初優勝まで11年かかったので、もうやめようか、と考えた時もありました。でも、自分が何をしたいのかを明確にすると、期待を力に変えることができるようになりました。それは優勝した後からうまくなったというか、勝って次のステージに行った時にまた見えてきたところがあったので。遠回りしたけど良かったなというのがあります。
同世代の皆さんにも、セカンドキャリアに向けて、職種を越えて頑張っていただけたらと思います。トーナメントを見に来てくださる方もいらっしゃるので、「宮里、まだ頑張っているのか、じゃあ自分も頑張ろう」と思ってくれたらうれしいです。
-

今日は、大和ハウス工業の社員の方にも対話に参加してもらえたら良かったですね。次に宮里さんがトーナメントで優勝したら、みんなで祝勝会を開くのもいいね。
-

ぜひそうしてもらえたらありがたいです。


4
まとめ
自分のフィールド(業界・職場)を、多様な人々と共に、より楽しく、より進化させ、次世代に継承していこう。その思いは、新たな分野への挑戦や学びにつながり、キャリアの可能性と、豊かな人生への扉を開いていく。
対談の様子を動画でも
ご覧いただけます。
※本稿に掲載した各コメントは、対話者の経験に基づく個人の感想です。