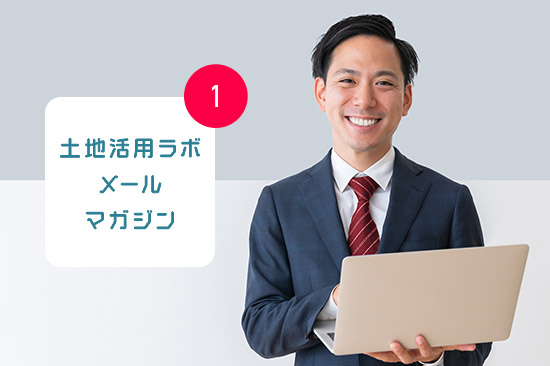コラム No.27-112
コラム No.27-112秋葉淳一のトークセッション 第2回 価値を分解し、「おもてなし物流」を再設計する株式会社ビームスホールディングス 執行役員 竹川 誠 × 株式会社フレームワークス 会長 秋葉淳一
公開日:2025/08/29
バケットが外に出るHaiPick SYSTEM

秋葉:今回導入されたACR(Autonomous Case-handling Robot)と呼ばれる自律走行型のロボット「HaiPick SYSTEM」について伺います。実際の運用では、バケットが外まで出て行くこともありますよね。この仕組みの導入は、まさにビームスさんが目指される、全体効率化が実現する仕組みだと思いました。
竹川:HaiPick SYSTEMは、バケットが自由に出て、入荷のエリアまで行って、荷物を入れて中に戻ってくる。その後ソーターのところまで行って、出したものがまた戻ってくる。実は、この外に出るということがすごく大きなポイントです。新センターでは、マルチテナント倉庫の制限がある中でも、天高5.5mを最大限に活用し、防火壁の影響を受けずに高い保管効率を実現しています。
ピッキングステーションまでバケットが自動搬送されることで、ピッキング作業がゼロになり、棚入れ作業も自動化(ゼロ・ストック)され、最大の工数削減になります。
秋葉:その外に出ていくプロセスは、当然センターごと、会社ごとに異なると思うのですが、トータルでどれくらいの数のバケットをどう用意して、どう回していくのか。そこはどのようにシミュレーションをされたのでしょうか。入出荷のステーションにある棚の数に応じて割り当てるようなイメージでしょうか。
竹川:入荷と出荷のステーションは分かれています。棚に対して57台のHaiPick SYSTEMが稼働しており、1回で6ケースの出し入れができます。在庫状況とソーターへの投入スピードを考えました。あと何バケット処理するか、バッファをどれくらい持たせるかを考えて設計しました。
秋葉:まず、保管するのにどれくらいの棚が必要なのかを考えて、その上で、出し入れの最大値を想定して、AGV(Automated Guided Vehicle:ガイドに沿って走行する無人搬送車)の台数を決めて、ステーションを決める。そのような感じでしょうか。
竹川:そういうことになりますね。
秋葉:センターの中をバケットが動き回っているわけですから、効果は大きいですよね。
竹川:バケットを外に出せないとなると、いくらポートに早く運べたとしても、結局1ケースずつ誰かが対応することになってしまいます。シャトル型(保管ラックの間をシャトル〔台車〕が水平に移動し、棚からケースやコンテナを取り出す自動倉庫システム)にしても、シャトルのレーンごとに人が必要になると思います。
秋葉:シャトルもそうですよね。最近では、シャトルではなくてクレーンを使って、床面もコンベヤーではなくAGVを走らせるような仕組みを開発するベンチャーも出てきました。ベンチャーは自分たちで一から設計するので、棚やバケットのサイズも自由で、バケットも市販品をそのまま放り込めます。そうすると竹川さんがおっしゃったように、外と共用することができます。そこも強みになると思いました。
竹川:それは本当に大きいですね。物流センターの業務は一か所だけ効率化できても意味がなく、全体として業務効率を改善する必要があります。
秋葉:結局そこでセパレートされて、出し入れの部分がボトルネックになってしまう。「じゃあステーション増やせばいい」と言っても、その分「人を増やしますか?」という話になります。
竹川:おっしゃる通りです。そこは本当にこだわって、リクエストして見つけてきてもらいました。われわれの今までの経験値から、そこがボトルネックになることは見えていましたから。
価値を届ける「おもてなし物流」

秋葉:先ほど、今後さらに拡大していくECにも対応できるセンターというご紹介がありました。店舗向けもEC向けも一つのセンターでこなしていくのは、物流センターとしてけっこう特殊なケースですよね。
竹川:一般的に、EC用の在庫と店舗用の在庫を分けて管理するところがほとんどですが、ビームスでは、在庫の考え方が他のセンターとは異なり、在庫はすべて一元管理しています。たとえば、商品Aを店舗用にも保管して、EC用にも保管します。われわれはそれを一元管理で、同じ在庫から店舗にもECにも引当がかかるような管理をしています。一元管理にはさまざまなメリットがあります。在庫を2箇所で管理していると、たとえばECの売上が好調で在庫がなくなった場合、店舗在庫から補充することになります。そのとき、ソールドアウトになる前に補充をかけるとしても、ECでも店舗でも売上が立てられない在庫が発生してしまいます。いわゆる横持ちの状態ですね。それに、ソールドアウトしてから補充するとタイムラグも発生します。われわれは、在庫が10あれば10すべてをECサイトに反映させて、潤沢にECでの販売ができます。店舗だけでなくオムニチャネルにも力を入れている中で、その商品を欲しいと最初に言っていただいたお客様にお届けできるようなシステムを構築しています。
秋葉:まさに大事なのは、「お店が欲しいか」ではなく、最終的に「買う人が欲しいかどうか」という視点であって、ECで売れるのか、店舗で売れるのかは本来関係ありませんよね。
竹川:おっしゃる通りで、それによってサービスレベルが落ちてしまうと思います。われわれは、2016年からそのような思想のもとに一元管理を進めてきました。最初は在庫精度が疑わしくて、10点あれば7点ぐらいをECサイトに反映させていましたが、RFID(Radio Frequency Identification:モノや人を識別する自動認識技術の1つ)を導入してからは、入りと出の精度が向上したことでセンター全体の在庫精度も上がり、今では10あれば10を反映しています。
秋葉:そこでもRFIDが活きてくるのですね。
竹川:そうですね。RFIDで簡易的に検品作業ができることには大きなメリットがあります。
秋葉:私も新センターを見せていただきましたが、物流の知識があまりない人が見たら、HaiPick SYSTEMとCUEBUSCUEBUS(リニアモーターを使用した世界初の立体型ロボット倉庫)ばかりに目がいってしまいそうだと思いました。しかし、ベーシックな土台があるからこそ全体としての仕組みができるわけです。
新センターは、ECも含めたすべての在庫を一元管理で運用することを前提に設計されていますが、そういった思想や設計方針が抜けた状態で、「HaiPick SYSTEM」と「CUEBUS」だけを見てしまうと、まったく違う印象を持たれてしまうのではないかと思います。
竹川:機械の導入は、いわば1ピースだけですからね。それがすべてを解決するわけではありません。機械ができるところは機械に任せて、人がやらなければいけないところは人が担う。その「人でないとできないところ」はECの根本にも関わっていると思います。手前味噌ではありますが、ビームスのギフトサービスのクオリティは、商品が届いた時には本当に喜んでいただけるような、非常に高いレベルだと自負しています。われわれはそれを「おもてなし物流」と言っているのですが、気持ちを入れるべきところには人をアサインさせる。そういうことができているのも、秋葉さんがおっしゃるような一つの全体の仕組みにつながっていると思います。
サプライチェーンマネジメントとは価値を届けること
秋葉:先日、ある方から「サプライチェーンマネジメントってどういうことなんですか?」と聞かれたことがありました。多くの人は、モノを届ける話、生産性を上げる話だと思っているかもしれません。しかし私の考えでは、サプライチェーンマネジメントは価値を届ける話であって、モノだけの話をしても意味がありません。たとえば今お話にあったギフトであれば、最後のところでどういう形でお客様に届けるか、という話になります。どういうものが喜ばれるかは、サプライチェーンを遡ってきた情報から導き出していくので、単にモノを運ぶだけの話ではないのです。

竹川:先日まさにそんな話をしていました。最近はデータドリブン経営など、データを活用していろいろやっていこうという話があります。ではデータを使って何がしたいかというと、やっぱり価値を生み出すことなのだと思います。その価値を分解すると何になるのかというと、まずは利益を上げることですが、それだけではないですよね。お客様にどうサービスするか、購買体験をどれだけ高められるかなど、お客様への還元がサプライチェーンの中にないといけない。効率化ばかりの話ではありません。
秋葉:もちろん効率化もしていかないと、無駄なところにコストがかかってお客様に還元できません。でもそこはコストの話だけではありません。同じ商品だったとしても、ギフトの包装が欲しくて、高くてもそちらを選ぶ可能性も当然あるわけです。それってやっぱり価値ですよね。モノが溢れている時代において、物的なモノだけでなく、「価値」という捉え方がより重要になってきているように思います。
竹川:「価値」という言葉は抽象度が高いため、分解して考える必要がありますね。
秋葉:私たちは物流のシステムやオペレーションに関わる人間ですが、一方で一消費者でもあります。だから実際にはすごく身近な話をしていて、分解できるはずなのです。だけど、ついそのことを忘れがちになってしまいます。
ビームスさんのLX-プロジェクトのお話の中で、アップサイクルやリユースといった、サステナブルのキーワードも出てきていました。ただ、いわゆるサステナブルの前に、返品されてきた商品のリセールの時間をどう短くするか、シーズンが変わってしまう前にどう買ってもらうか、といったサイクルもありますよね。
竹川:今力を入れているのは静脈物流(返品・回収された商品を再販・再利用につなげる戻りの物流のこと)です。一度店頭に出した後は、シーズンを終えて戻ってくる、入れ替えで戻ってくるなど、さまざまな戻しがあります。それをいかに高速で処理して、EC販売につなげていくか。そこは物流の知恵の出しどころだと思っています。
これからまたRFIDを入れるのですが、そこで特に力を入れなければいけないのが、検品の正確さと、あとはやはり犯罪のリスクもあります。返品の際には、真贋を見極める能力も必要になります。数としてそこまで多くはありませんが、そこはこれからの課題で、しっかりしたフローを入れていかないといけないと思っています。EC販売では、間違ったものがお客様のお手元に届いてしまうことも起こり得ますから、「価値」に直結する話です。
秋葉:これはビームスさんだけの話ではありません。1社だけで対応する方法も当然ありますが、そこにはどうしても人の手が必要で、高い精度で対応しなければなりません。各社で人を抱えて、場所を用意して、個別に対応していくのは現実的なのでしょうか。
以前ドイツに視察に行った際に、オットーの返品専用センターを見てきました。オットーグループの中に何社もあるのですが、そこはオットーグループ全体の返品専用センターとして集約されていました。そこでは、全体の80%超が48時間以内にリセール可能で、補正が必要なものがあっても、90%以上が72時間以内に再販することができます。
竹川:これからのECでは、返品のハードルを下げていく必要があると思っています。試しやすくて買いやすい状態が理想なので、やはり静脈物流をどう構築していくかが重要になってきます。それに伴ってリスクも増えてきたとき、各社で対応するかは別として、そこは工夫していかなければならないですね。

秋葉:ビームスさんが創業50周年を迎えられるということで、それこそセレクトショップ黎明期からの歴史をお持ちです。買い物に対する考え方も行動も、大きく変わってきたと思います。私たちが買い物をしてきた時代と、私たちの子どもたちが買い物をしている環境はまったく違いますよね。お店に行く時間を考えると、まとめてオーダーして、持ってきてもらって、家で試着して、要らないものは返すというプロセスのほうが、彼ら彼女らにとっては楽だと思います。
竹川:われわれは「返したら申し訳ない」という世代ですよね。
秋葉:そこには世代間の感覚のギャップもあります。
竹川:体験はお客様へのサービスであり、買いやすさは購買につながると考えています。
秋葉:そんな気はしますね。それもひとつの価値ということです。
少し違う目線で考えると、先ほどの犯罪リスクの話にも関わってくるのですが、日本人は比較的性善説で、「みんな悪いことをしないよね」という前提の下にいろいろな仕組みが考えられているところがあると思うんです。一方、欧米人は比較的性悪説です。これは「秋葉は悪いやつだ」というような意味ではなく、「人間は過ちを犯すものだ」ということを前提に仕組みが考えられているのだと思います。静脈物流をやるとして、そういう発想が私たちにできるでしょうか。意識しているか無意識かは別にして、人間は過ちを犯すもの。これは倉庫のオペレーションでも言えることで、「人がやっているから間違いが起こる」という話と同じです。
だからこそ、間違いを起こさせない仕組みをどうつくるかが大事です。それは消費者に対してもそうですし、入ってきた商品のチェックでも同じです。物流の笑い話に、検品しているのにエラー率が下がらないからと、二重検品を始める話があります。何重にチェックしたところで100%にはなりません。「ちゃんとやるはずだ」という前提があるから、二重三重にすれば大丈夫だろうとなってしまう。しかし、この人がいない時代にそんな話はありえません。
竹川:たしかにそうですね。
(次に続く)