インタビュー
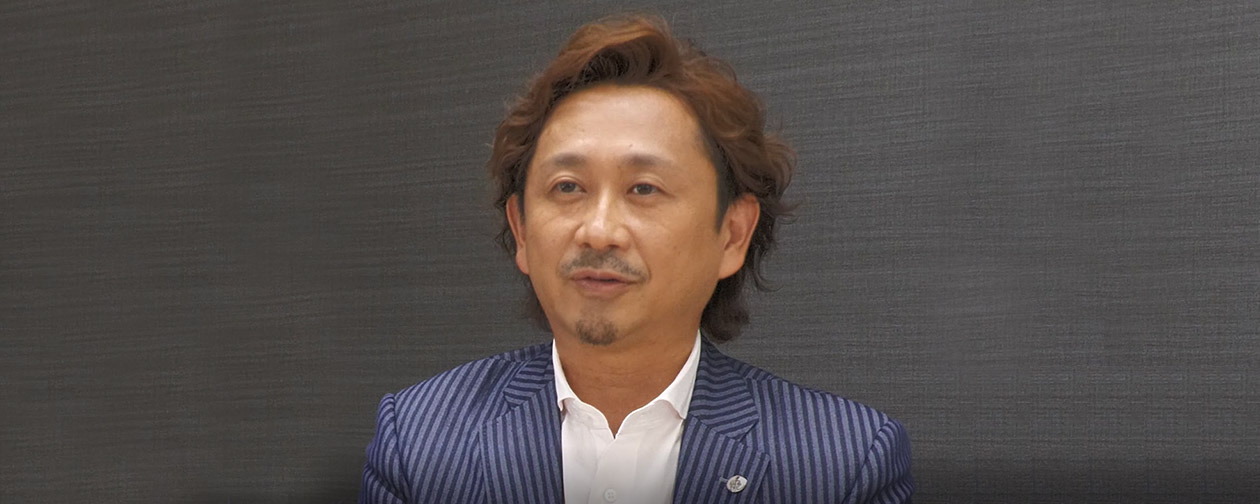
税理士法人ブレイス 野口 大樹税理士
税理士はコーディネーター
ワンストップの窓口として活用してほしい
10年間で土地活用の流れが変わった
「税理士法人ブレイス」のメインのお客様は中小企業の方々で、顧問税理士として関わっていますが、当事務所がある東京都板橋区は土地柄地主様が非常に多く、農家の方も多くいらっしゃいます。そのため、「土地をどう利用していくか」「資産税や相続の対策をどうするか」といった案件が多くなります。そこをどうコンサルティングしていくかが大事だと考え、事務所のブランディングの一つとして力を入れて取り組んできました。
この10年間で土地活用の流れは変わりました。相続税の改正によって基礎控除額が下がり、相続税額自体が上がってきたことが一番大きな理由だと思います。相続税がかかる方が増えて、何らかの対策を打たないと、今まで維持してきた不動産を維持できなくなってしまうという状況もありますし、単純に、相続税というものが世の中に認知されてきたこともあります。
ただし、税金のことはもちろん大事ですが、それは一つの結果です。相続は、後で対策しようと思ってもなかなかできないものです。「どのように資産を守っていくか、活用していくか」ということに注力すべきであり、お客様の興味も本質的にはそこです。
お客様は農家の方のほかにも、事業をされている方もいらっしゃいます。もともと農地だった土地が多いのですが、当然、地域によっては工場やビルを持っている方もいらっしゃるので、まずはお客様が今持っている資産を把握します。ニュースで見聞きし、高額な相続税がかかるのではないかというイメージが意外と先行しているものです。安心していただくためにも、まずは現状を分析します。今、万が一のことがあったらどのようなことが起きるのかをお伝えしたうえで、その後に、「どう守っていくか」「今、活用したほうがいいのかどうか」など、トータルでコーディネートしていきます。
時代によって変化していく土地活用
時代によって、土地活用のニーズも変われば、施設のバリエーションも広がっていくものです。昔は、一般的に、土地活用といえば賃貸住宅やマンションを建てることが多かったと思います。今は、空室率の心配がありますし、土地も用途地域によってさまざまです。われわれ税理士も勉強していますが、TKCの協定企業である大和ハウス工業さんに、その土地はどのように有効活用するのが一番適しているか積極的に提案していただいて、それをもとにお客様にご説明していくという流れが一番多いです。
土地活用の事例としては、最近では介護施設があります。やはり介護施設はこれからのニーズが高い施設です。また、珍しい事例ではガレージハウスがありました。このような用途は、われわれだけではなかなか発想できないので、そこはやはり大和ハウス工業さんに一日の長があります。大和ハウス工業さんの魅力は総合力と提案力です。どのような土地、不動産であっても、何かしらアイデアを出してきてくれるのではないかという安心感があります。用途に合ったアイデアをいただきながら、その中でどれが一番良いのかをお客様と一緒に考えます。
一方、土地活用はニーズだけでなく、収益力やその後の相続税の評価といった問題も出てきます。だからこそ、大和ハウス工業さんの観点と、私ども会計事務所の税務の観点の両方が必要です。何棟まで建てていいか、もう少し大きくしたほうがいいのか、小さくしたほうがいいのか、建て方も含めて、そういったことを一緒に考えるので、お客様には安心して物件を建てていただけるのではないかと思います。会計事務所が言った、営業の人が言ったというのではなく、チームとして動くので、そこが大きな強みだと思っています。
今は皆さん、情報を非常に多く持っています。相続される方は、いろいろな権利の部分も含めてよくご存知です。昔は、長男が全部継ぐのが当たり前という時代がありました。しかし今は、それぞれ自己主張をする方が増えて、遺産分割協議をどうしていくかを考えたとき、「相続が起きてから何かをするのでは遅い」ということを皆さん理解しています。事前に、親が元気なうちに何かしなければいけないという意識が強くなってきているので、今のうちに土地を活用して、相続税対策を取りつつ、さらに「この施設を誰が相続するのか」というところまで、総合的な提案をしてほしいと思う方が非常に増えました。土地活用は投資金額が大きくなりますから、もちろん簡単にはいきませんが、次の世代の方たちが一生懸命考えているので、比較的スムーズに相続が進んでいくのではないかという気がします。
少子化が進み、お子様がいらっしゃらない方の相続も増えています。昔であれば、「誰が相続するのか」「どっちが相続するのか」が問題でしたが、今はそれこそ「相続する人がいない」というご相談も多くなっています。解決策はなかなかないのですが、やはりこれに関しても事前に考えておくことが大切です。おい、めいなど、親戚の方と養子縁組をするなど、場合によっては、そこまで深く踏み込まないと相続がなかなか進んでいきません。税金の話だけではなく、「今後○○家の資産をどう残していくか」というスタンスで考えていかないと、財産を残していくのが難しい時代になっています。
税理士はコーディネーター。
ワンストップの窓口として活用してほしい
私は税理士なので、当然、税金について考え、税金の計算はしますが、それだけでは解決できないのが相続です。私は、税理士はプランナーやコーディネーターのような立場だと思っています。お客様から見てわれわれを中心に、地域の信用金庫や金融機関、大和ハウス工業さんをはじめとしたハウスメーカーの方々、土地家屋調査士、司法書士、場合によっては弁護士まで、いろいろな方を巻き込んでいく。それをわれわれがトータルでコーディネートしていくわけです。税理士が常に中心にいるのは、われわれ税理士が一番動きやすいからです。そういった意味で、コーディネーターという役割としてお客様と接しています。
TKCには月次巡回監査というものがあります。例えば、多くの土地をお持ちの地主様は管理会社をつくったり、法人化したりします。その法人や管理会社と顧問契約をして、顧問税理士として毎月お客様のところにうかがい、帳簿を確認して監査するのが月次巡回監査です。それによって毎月お客様とは必ず顔を合わせることになるので、建築の提案がきたときにもすぐにお客様に確認することができます。
月次巡回監査は、2代目の方、次の事業承継者の方と顔をつなぐ場でもあります。顔をつないでおかないと、先代の方が亡くなったときに縁が切れてしまう可能性もあるため、必ず毎月うかがうような仕組みづくりをしています。その中で、「相続税の試算をしませんか」「今はこの土地をうまく使えていないから、もっとこういうふうに活用したらどうでしょうか」など、気づいたときにお客様にご提案します。待ちではなく、こちらから仕掛けていく。おそらく、これが扱う案件が多い最大の理由ではないかと思っています。
土地活用の今後
今、資産活用に関することを含め、いろいろな法律が変わっています。裁判や最高裁の判例によって、今までの考え方が適用しなくなってしまうのは往々にしてあることです。税務をうまく活用して提案することはもちろん大事ですが、そこに着目しすぎると、税金を下げることだけが目的になってしまいます。建築費用が上がり、利回りも昔ほど出ず、土地活用は決してそれほど儲かる商売ではありません。自分たちのお客様をどう守っていくか、どうしたら最小限のリスクで済むか、そうした全体としての気持ちをうまくくむことができないと、「別のところでやったほうが安い、高い」といった価格だけの話になってしまいます。大事なのは「お客様のどうしていきたいか」です。
お客様には「最後に大事なのはお金ではないですよ」と言っています。そうしないと話が進まないですし、それが本来の姿です。ただ、土地活用をするなら、今の税制をきちんと把握し、うまく活用したほうがいい。税金と土地活用のどちらが先かと考えたとき、「税金が先ではない」ということを意識しています。

