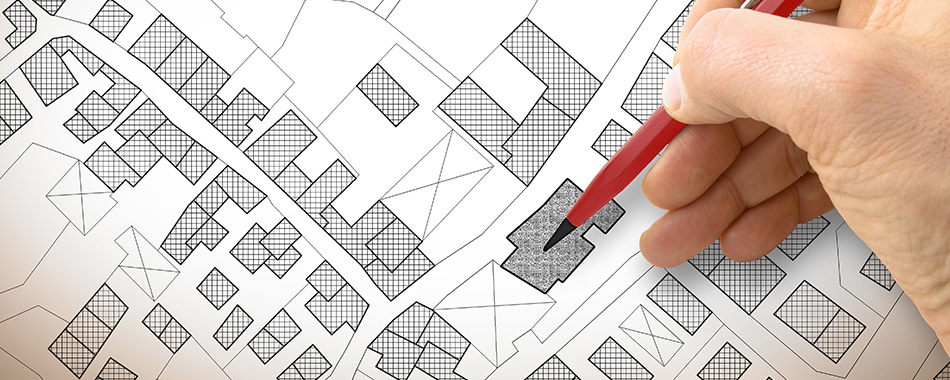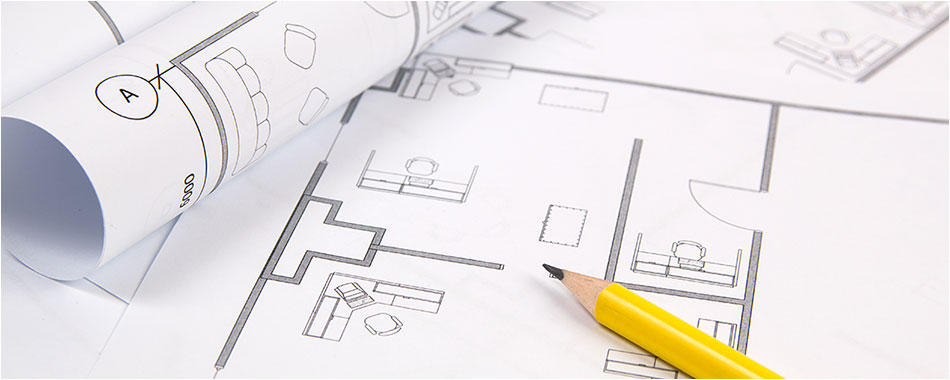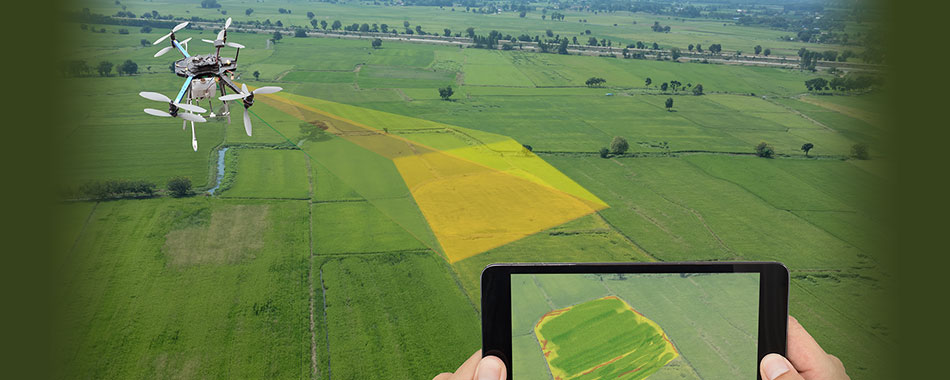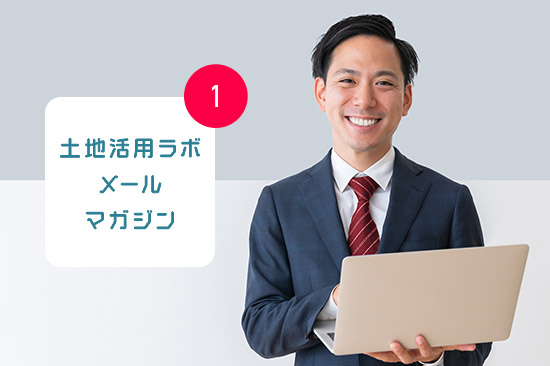コラム No.53-89
コラム No.53-89戦略的な地域活性化の取り組み(89)公民連携による国土強靭化の取り組み【51】公的不動産(PRE)の流動的活用による地域創生事例
公開日:2025/09/30
1995年に不動産特定共同事業法(FTK法/不特法)が施行されて以降、高額な不動産を小口化して多くの投資家等から出資を受け、不動産の流動化を促進することで、オフィスビルや住宅、商業施設、福祉施設など、特定の収益不動産を取得・運用して地域インフラ等社会資本を整備する事例が増えています。今回は、公的不動産(PRE)の再生、地域の再開発に焦点を当てて、好事例をご紹介します。
不動産証券化制度の背景と効果
不動産証券化は、1990年代初頭のバブル経済崩壊による地価の下落などを契機に進展したといわれます。不動産を所有する企業等は、下落する不動産の保有リスクを軽減化するために、売却などにより遊休不動産を資産から外し(オフバランス)資産をスリム化、不動産の所有と経営を分離することで、経営体質を改善する動きが活発化しました。一方、不動産投資分野では、不動産の値上がり益(キャピタルゲイン)のみでなく、賃貸など不動産運用によって得られる収益(インカムゲイン)を重視する考え方が普及した時期でもあります。
そのような経済環境、時代背景の中で制度化されたのが、「不動産特定共同事業法」です。この法整備により、不動産特定共同事業を行う事業体の要件や責務等が明確になり、不動産の小口化、証券化が法的基盤を得たことで投資リスクも軽減され、不動産証券化、流動化が促進されることになります。
その後、1998年から2013年にかけて法改正が行われ、特例事業者として特別目的会社(SPC)に拡大(規制緩和)する法整備がさらに進んだことで、FTK(不動産特定共同事業)スキームによる地域再開発が活発化しています。
例えば、公的不動産を活用して地域密着型の都市開発を行う場合に、地域出資SPC(特別目的会社)を設立することで、地元企業や住民、金融機関、公的機関から、小口で出資や融資、補助金等の資金を調達し、地元事業者や住民ニーズに応じた施設やサービスの開発・改修プロジェクトに必要な原資が確保できます。対象不動産を提供した公的機関はSPCより不動産売却代金や賃借料を取得、施設等完成後には、SPCは施設利用者から利用料や賃貸料を回収することで、出資・融資者に対して配当や元利金を支払うといった、官民連携による地域循環型のスキームが創出されます。
FTKによる公的不動産(PRE)を活用した地域創生事例:敦賀駅西地区開発
2022年9月、福井県敦賀駅前にTSURUGA POLT SQUARE 「otta」が誕生しました。敦賀市は福井県の西に位置し、敦賀駅は金沢、東京方面と関西方面、中京方面の結節点となる駅です。その北陸の玄関口とも言える敦賀駅西口に、市民と来訪者の交流や賑わいの創出の拠点となるよう、ホテル、飲食店、物販店、子育て支援施設、知育・啓発施設が配置され、また中心には来訪者や市民の憩いの場として芝生の広場が広がり、イベント開催のスペースとしても活用される「駅西広場公園」が整備されています。
敦賀市では、2024年の北陸新幹線敦賀駅開業に合わせて、市所有の敦賀駅西地区を敦賀の玄関口にふさわしい賑わい・交流拠点とするため、2005年度から土地活用について検討を開始し、2016年には「駅西地区土地活用に係る整備の方向性について」を策定、敦賀市としての整備方針を示しました。それに基づいた市場調査を経て、民間資本の活用が可能との結論に達し、FTKのノウハウを持つコンサル企業を公募により選定後、同社のサポートの下で不動産特定共同事業特例事業者(SPC)を設立し、国・自治体の補助金、地元金融機関の融資、投資家からの出資金により総工費約27億円の資金を調達しました。その資金を元に、SPCが市有地を定期借地し、知育・啓発施設や飲食・物販施設、ホテル等を建設・所有するとともに、施設を市や施設運営事業者が借り受けるなどの官民連携手法により運営されています。
旧村上邸再生利活用ファンド事業
鎌倉市の旧村上邸再生利活用ファンド事業もFTKの仕組みを活用した好事例です。鎌倉市が寄贈を受けた古民家である旧村上邸は、地域における歴史的・文化的に貴重な建築物であることから、鎌倉市は保存活用を行う必要があったため、FTK手法に詳しい事業者を選定し、研修施設や地域コミュニティ施設として改修する資金(約900万円)の調達や施設活用について、行政及び地域民間企業、市民の3社共創で活動できる仕組みとして、クラウドファンディング型FTKを採用しました。その後2019年に、旧村上邸は「鎌倉みらいラボ」としてオープン、運営事業者は鎌倉市と定期賃貸借契約を締結し、施設利用料収益を元に事業運用を進め、企業研修や市民活動の場として活用されています。
FTK手法は、公的不動産の再生のみならず、空き家の改修や市民サービスを提供する民間事業への活用事例が増加しています。民間資本を活用することで、公的不動産の開発・改修に係る行政費用を抑制できるとともに、事業に関連する地域民間事業者や投資家、市民等に対する「まちづくりの自分事化」(参画意識)の醸成や、地域外からの施設来訪者等との「関係人口の増加」に寄与できるのではないでしょうか。