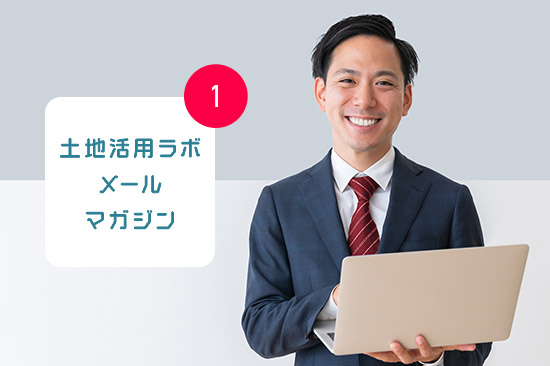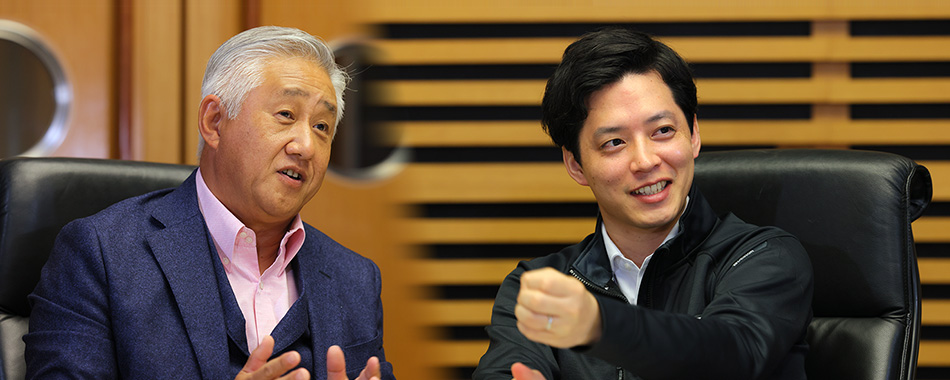 コラム No.27-107
コラム No.27-107秋葉淳一のトークセッション 第3回 LexxPlussが切り拓く次世代の物流インフラ株式会社LexxPluss 代表取締役 阿蘓 将也 × 株式会社フレームワークス 会長 秋葉淳一
公開日:2025/03/31
自動搬送ロボットが変える物流現場:Xフロンティアでの取り組み

秋葉:2022年12月から、SGホールディングスグループの次世代型大規模物流センター「Xフロンティア」に12台の「Lexx500(以前はHybrid-AMR)」が導入されました。私が最初に阿蘓さんに会ったのは、Xフロンティアでテストを始めていた頃でした。XフロンティアでハイブリッドのAMRを動かすことにどんなメリットがあるのだろうと思ったのを覚えています。当時の取り扱いの荷量はどれくらいでしたか。
阿蘓:Xフロンティアに入る物量の1%です。不定形貨物と呼ばれるもので、コンベアに乗らない棒状の物やテーブル、ゴルフバッグ、植木鉢などがあります。1%なので本当に少ないのですが、時々ポンと出てきます。99%はコンベヤーの仕分けシステムで回して、1%は一つひとつ見て対応していました。
秋葉:1%しかないので、私からすると、何のメリットがあるのだろうと思ったわけです。
阿蘓:物量は1%なのですが、その1%を捌くのに約10%以上の人件費をかけています。1フロアだけで50人くらいのスタッフがいて、ほとんどが外国の方です。そこで荷物が出ないとボトルネックとなり、他がストップしてしまいます。それに、中継センターを大きく作っていて、24時間稼働なので、全体の物量が数十万になればその1%も大きくなります。
秋葉:さらに片道は空なので、空荷のトラックを走らせているようなものですよね。
阿蘓:台車で持っていって、ばら積みなのでそのまま積んで、空台車を持って帰る。その作業を300メートルぐらいある距離で延々とやっていて、よく見ると、大変なので休憩している人もいるわけです。将来的にはドライバーのところまで持っていきたいという構想ですが、一気には着手できないので、ステップごとに費用対効果が出るようなところからやっています。この横持ち搬送(工場、倉庫、物流センターなど、社内の拠点間で行う貨物輸送のこと)だけでも、月間の走行距離にして約2800キロをロボットが走っています。
PoCを2回行った上で2022年12月に正式導入していただき、2年経った今でも活用していただいています。ハードもソフトも全部自分たちで作っているので、導入当初は未完成な状態で、正直不具合が多かったのですが、ソフトウェアもバージョンアップして補強しながらやってきました。ずっと運用していただいていて、2800キロなので2年間で地球1周半くらい走っていることになります。もともとそれを人手でやっていたわけです。
秋葉:荷物は1%なのに、10%の労力がかかっているとなると、費用対効果も大きいですね。
阿蘓:そこに投資をして効率を上げることが必要だったと思います。佐川急便さんのBtoBに荷量を絞って1個あたりの売上を上げる一方で効率化を目指すという観点において、Xフロンティアは重要な拠点です。佐川急便さんはすでに自動化をトライアルで試していたので、自動化に対する推進力を持たれていたのだと思います。物流特有のオペレーションの難しさはあります。有軌道型だと、ドライバーが来て、荷物が止まっていたら渋滞してしまいます。しかし私たちのハイブリッドの技術があれば、迂回もできますし、有軌道でカチッとやりたいところは決められます。LexxPlussは創業間もなかったのですが、導入という意思決定をしていただきました。
秋葉:1%に集中して搬送の自動化に取り組んだのが大きなポイントだったと思います。あっちもこっちもではなく、そこできちんとやる。そこでLexxPlussの製品の精度を上げていく。そうすると、社内外が取り組みを認めてくれるのと並行して、技術的にここまで来たから次はあちら側もやってみようと、動かしやすくなるのだと思います。大きい意味で自動化をしなければいけない時、1箇所に集中したやり方が重要なのでしょうね。
既存オペレーションとの融合と標準化

秋葉:物流施設には、必ずパレットと台車はあります。パレットにもいろいろありますが、パレットを運ぶのはフォークリフトという点で共通しています。だからフォークリフトのフォークが入る部分をしっかりさせておけば、極端な話、大きくても、分厚くても、材質がプラスチックでも木でも運べます。しかし、カゴ車は人間が押すことを前提にしているので、高さも幅もバラバラで、運ぶのが残念ながら人間です。フォークリフトのような共通のものがないわけです。それを搬送ロボットにやらせることになった時、バラバラのものに対して、フォークリフトのフォークが入るような共通部分をどう作るかという話がないとできません。今さらカゴ車側に共通部分を作っても仕方がないので、LexxPlussさんがロボットとカゴ車を繋ぐジョイント部分を工夫したのはすごいことです。結果から見れば簡単なことでも、なかなかそれをやってきませんでした。
カゴ車は種類が豊富です。カゴ車は流通されるものなので、1拠点でも種類があるのが当たり前です。多くの物流センターでは、荷主、それも発荷主や着荷主に合わせたものを運用しなければいけないので、たくさんの種類になってしまう。さらに古くて車輪が固まっているものもあったりして、人間だから重くても一生懸命やっていたのだと思いますが、人間だって大変だったはずです。
阿蘓:その辺りの標準化も合わせて進める必要があります。私たちのほうでも何でもつかめるように頑張りますが、両方の歩み寄りがあったほうが加速しやすいので。
秋葉:そのガイドラインを作るため、RRI(ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会)の物流倉庫TCにLexxPlussさんにも加わってもらって、NX総合研究所さん、Mujinさんと一緒に、令和5年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(物流施設の自動化に資するロールボックスパレットのモデルケース創出)を行ってもらいました。
カゴ車は納品先によって高さや幅をどうしても変えざるを得ません。配送効率を考えれば大きいほうがいいし、間口が狭ければ小さくしなければいけない。そういった要望があるのはどうしようもないことです。ただし、ロボットがカゴ車に荷物を積み下ろしすることを考えて、色や形、開き方をどうするか、ロボットが搬送することを考えて足回りをどうするか、ある程度ガイドを出すことによって標準化できるのではないか。実証実験をしていただいて、けっこう良いデータが取れましたね。
阿蘓:細かいことを言うと、カゴ車の板のどちら側に溶接するかで搬送システムのつかみやすさが変わってきます。メーカーによってバラバラで、設計によって外側に溶接されていたり内側に溶接されていたりして、本当に細かいのですが、実はそういったことも含めて自動化の障壁になっています。コストの話ではなく、コンセンサスを通す、標準化していくだけの話なので、そのような工夫ができてくるとばらつきもなくなり、お客様としても自動化を入れやすくなって進んでいくと思います。
LexxPlussが描く2035年の未来像

秋葉:創業から発見だらけの5年だったと思いますが、想定外だったことはありましたか。
阿蘓:会社を創業して5年なのでまだまだ経営者として甘いのですが、人に関する問題が一番大変ですね。事業の課題解決はある程度解決策がありますし、対策できますが、人の問題や組織の問題はそれぞれ個別解を探さなければいけないし、人間関係によっても違います。
秋葉:スタートアップではよく聞く話ですよね。スタートアップでなくても、会社がピボットをした時、急成長した時にも起こり得る話です。私たち周りから見ている人間からすると、そんなに気にすることではないとも思います。阿蘓さん1人が大変な思いをするのではなく、管理サイドがしっかりしているのであれば、オペレーションサイドで共感してくれる人、一緒に戦ってくれる人が入るとより一層加速できると思います。
阿蘓:ロボティックスと言われる分野は、ハード、メカ設計、エレキ設計、ソフト、クラウドシステムなど多岐に渡ります。組織が40~50人体制になったとしても、1チームは数人です。横断的に技術の総合格闘技のようなところがあるので大変ですね。人集めも大変です。エキスパートが入れば伸びるのですが。
秋葉:そこだけ伸びたからといって全体が上がるわけじゃないですよね。
阿蘓:おっしゃる通りです。ハードが弱かったらいくらソフトが良くても動かない。逆に、ハードを頑丈に作ってもソフトが良いけてなかったら効率は上がらない。全体のバランスをとって成長させていくという大変な領域です。
秋葉:製品が使われていくことで良くなっていくのではないでしょうか。その中で、物流・製造関係なく、搬送の現場で起こりうる課題を解決するノウハウも溜まっていきます。搬送を中心に攻めるのであれば、今あるサイズがいいのか、牽引できる重量は今のままでいいのか、そこで幾つかのレパートリーを持つとしたらどこに攻めていくのか。それを考えていくとどうしてもまた人依存になったりして、すごく面白いと思います。
一方で、物流目線で見ると、製造業の中、工場の中にも物流業務があり、公設市場の中にも物流業務があるという話になります。今までは物流として切り出していないだけであって、人がいなくなるのであれば、物流として切り出して、そこの搬送部分を自動化していく。私たちがお客様に提案して、持っている技術をそこにはめ込んでいくことができると、世の中のためにもなります。搬送は物流だけではないですからね。
阿蘓:市場は横断的にあります。市場が違っても潜在的な自動化のニーズは高く、特に搬送は存在悪というか、やらなければならないけどやりたくない、自動化したい業務です。工場、物流、公設市場もあるし、ショッピングモールもある。そういったところまでプラットフォームとして提供できるようにしていきたいですね。
秋葉:大和ハウスグループとしてもやることはたくさんありそうです。建物だけではなく、運営上においても「こうしたらこうなりますよね」というところまで描かないといけないと思います。グループ全体で考えると、大和ハウスが立ち上げた、ストック施設を扱うリブネス事業は、まさにこれと同じ考え方です。物を売って終わるのではなく、メンテナンスして使い続けてもらう、住み続けてもらうため、あるいは事業を継続するためにどうするか。リブネスの場合は結果から始まっていますが、提案の段階からそれを考えて提案することが必要になると思います。
これからは人手不足の問題がますます大きくなるので、皆考えざるを得ません。考えざるを得ない機会だからこそこうした提案をしていく。それが仕事につながるかどうかは分かりませんが、提案をしてお客様と会話することによって課題が見えてくるし、課題が見えれば、それをどうやって解決するか考えることができます。
最後に、LexxPlussは創業から5年経ちました。この後の5年はどうしていきたいですか。

阿蘓:次のファナック、次のキーエンスと呼ばれるような産業機器メーカーになることを目指しています。2035年に時価総額1兆円を超える会社になることが私の目標です。どう受け取るかは人によりますが、お隣の国である中国では、創業10年で1兆円を超えている企業があります。ものづくりだから難しい、IT業界でないとできないという話ではなく、お隣の国には実際にそういった企業が次々と立っています。なぜ日本からそれが生まれないのだろうというのが、私のフラストレーションとしてあって、日本をもっと良くしていきたいと思うのです。遡ればファナック、キーエンスのようにグローバルに活躍して、ものを作って、自動化を促進している企業が出てきたのだから、今の世代でも奇跡ではなく、実現できる話だと思います。われわれとしてはそこを目指してやっていきたい。その最初の階段を一歩踏み出したところです。
秋葉:できない話ではないと思います。フレームワークスが大和ハウスグループに入ったのが2012年で、その時のグループ全体の売上が約2兆6,000億円でした。それから11年後の2023年に倍の約5兆2,000億円になっているので、その差は2兆6,000億円で、ボリュームとして取れない話ではありません。
一方で、「日本だから」と言われてしまう理由の一つが、提案する時、どこに入れた実績があるか、どこで稼働したかを聞かれることです。これは、人が大勢いる中で、市場が膨らむ時に失敗したくないという話です。人もいなくなって、今までの延長線上でできないとすると、そもそも今までと違うことをしなければいけないし、チャレンジしなければいけない。働いている人のマインドが変わらないのであれば、マインドが変わった会社に勝てません。これからマインドが変わる会社が増えていくと思います。会社自体もそうだし、マネジメントする層でも、そういう人たちの年齢が高くなってくるので余計にチャンスだと思います。そういう意味で、佐川急便さんが、当時実績がなかったLexxPlussさんと一緒にやろうと決めたのはすごいことです。
阿蘓:佐川急便さんが意思決定をしてくれなかったら、今のわれわれは多分なかったと思います。そのような人が増えると、そうした機会をチャンスにものにしていく私たち以外の企業もより出てくるし、業界自体が発展していくと思います。
秋葉:昔と比べると、「どこどこで採用されているからうちは入れられない」と言われることが減ってきています。まだ言う人もいますが、そこは変わってきているので、エクスパンドするチャンスが昔より増えている気がします。LexxPlussさんの成長はまだまだこれからで、LexxPlussという器が崩壊してはいけない。阿蘓社長にとっても、この5年間はどう過ごすかという意味で重要だったと思います。ただ、LexxPlussに可能性を感じている人たちは大勢いて、5年間を見てきているので、そろそろアクセルをもう1回踏み込むことを考えてもいいのではないでしょうか。大きなチャンスが来ている気がします。
阿蘓:チャンスは来ていると思います。われわれもよりブラッシュアップし始めて、つかみどころが分かってきたのもありますし、市場自体も、自動化と言っている企業が増えていて、業界で自動化の機運は高まっていると思います。担当者ベースでも、自動化は必要だけど何をしたらいいか分からないというレベルの人よりも、何がやりたいか自分で考えて動いている人が増えてきていると感じます。
秋葉:コロナ禍をきっかけに建築原価も上がってきて、床代が下がる要素がないとなれば、オペレーションをどうやって設計し直して効率的にやるかを考えないといけません。製造業が何十年か前に求められた状態に近くなってきていると思うので、LexxPlussさんには期待しています。
本日はありがとうございました。