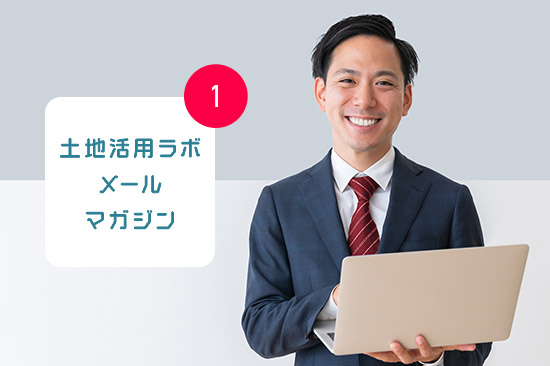コラム No.27-113
コラム No.27-113秋葉淳一のトークセッション 第3回 地域とつながる、「サステナブル・パーク」としての物流センターへ株式会社ビームスホールディングス 執行役員 竹川 誠 × 株式会社フレームワークス 会長 秋葉淳一
公開日:2025/09/30
地域と共に育てる、マルチファンクショナルな拠点

秋葉:今年6月に、大和ハウス工業も一緒にやらせていただいた「深川マルシェ」が開催されました。このイベントは、ビームスさんという会社のイメージだけでなく、物流センターのイメージをどう変えていくかという点でも、大きな意味を持つ取り組みだったと思います。
竹川:大和ハウスさんのご協力のもと、敷地内の空いたスペースを利用してマルシェを開催しました。少し話が前後しますが、今回の移転にまつわるさまざまな取り組みは、「サステナブル・パーク」構想という、私たちの物流戦略の下で進められました。
秋葉:どのような構想なのでしょうか。
竹川:サステナブル・パーク構想は、物流センターの役割を、機能・ヒト・サステナブルを軸に、未来視点で考えた物流戦略です。この構想は、「マルチファンクショナル拠点」「次世代の物流網」「システム/デジタルとの協働」「すべての人が活躍するしくみ」「エネルギー/環境ファースト」という5つの要素から成り立っています。これまでお話ししてきたロボティクス化とRFIDのブラッシュアップは、「システム/デジタルとの協働」に基づいて実施されました。
今回の深川マルシェは、「マルチファンクショナル拠点」という考えに基づくものです。「マルチファンクショナル拠点」とは、物流拠点を、物流機能に留まらないコミュニティ、イベント、体験を共有・共感する場にすることです。たとえば、飲食店・店舗・ショールームなど、お客様や取引先様と接点が持てる機能をつくって、地域の方と新たなコミュニティの場を創出します。
たいとる
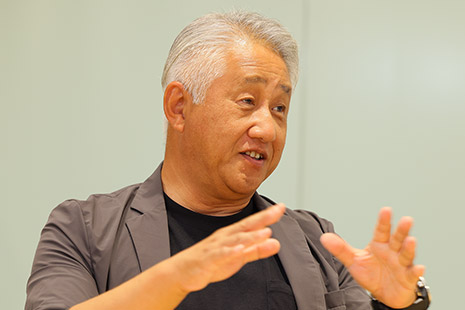
秋葉:物流センターにはどちらかというと、閉鎖的なイメージがありますが、地域との関係性を築いていくわけですね。
竹川:ただの物流センターではなく、地域共創の場、共感を生む場所をつくりたい。そういう意味でも、この深川マルシェはとても良い取り組みになりました。「あそこにビームスのセンターがあるよね」というだけでなく、センターがあることで地域の方々と繋がることができたのは、本当に良かったと思っています。今は2週間に1回、清掃活動も行っています。地域の方に、「あそこにセンターがあってよかったね」と言われるくらいにしたいですね。
秋葉:マルシェはとても好評だったようですね。
竹川:「マルチファンクショナル拠点」の一機能として、ビームスでは、サステナビリティの観点から、社会課題解決や社内貢献につながることを目指して、B品・廃棄予定品の倉庫祭の実施を行っています。深川マルシェでも、地域に還元できればと物販を行いました。大変ご好評をいただき、その売上金は江東区に寄付しています。住民の方々はもちろん、行政ともしっかり繋がっていきたいと思っています。
秋葉:マルチファンクションということですが、当然そのひとつは物流としての機能になりますよね。それ以外にどんなことを考えていますか。
竹川:まずは地域共創ができる場所にしていくこと。それから、物流拠点内にある撮影スタジオを、さまざまなコンテンツ発信にも対応できるように拡充・多機能化させていきたいと考えています。これからのECやメディアを使っての販売に対応するため、旧センターでは200坪だったものを500坪に拡張、5レーンから10レーンに増やしました。
また、マルチファンクション×サステナビリティの実践という文脈で言えば、センターをリサイクル、リユースの拠点として活用する可能性もあります。さらに、リサイクルなどの循環型プロダクト機能や、リユースといった循環型事業機能の強化を目指しています。これを実現するため、アップサイクルやお直しといった機能も持ちたいですね。
秋葉:マルチファンクションは、本当に実現していただきたいと思います。周辺地域の方々からすると、急に大きな建物が建って、車がどっと増えることで、どちらかというと悪いイメージが強くなることもあると思うのです。だからこそ、それを理解した上で、地域の方々とどうやってコミュニケーションをとるかが大きな鍵になると思います。
竹川:一般的に物流倉庫は駅から遠くに立地することが多いですが、今回は都市型のセンターで、われわれはそこに「居させてもらっている」という感覚があります。住んでいる方と非常に近いセンターなので、意識的にコミュニケーションをとって、嫌われないようにしたいですし、長くいられるようにしたいですね。
秋葉:都市型のセンターというのは相当意識されていますか。
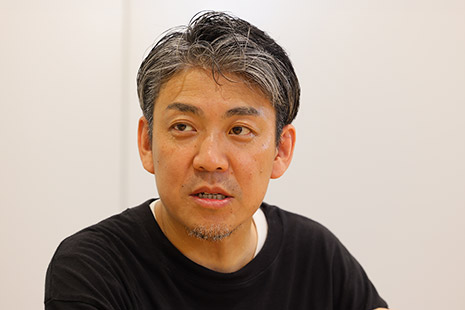
竹川:東陽町も都市型のセンターだったのですが、20年という年月の中で、スタッフはそこを中心に生活基盤を築いてきました。それを崩さずにいられたことは、私たちにとって大きな享受だったと思います。新センターはスタッフが通えて、駅からも比較的近いです。ただ、すぐ目の前にはマンションもあるので、地域の方々とのコミュニケーションをしっかり取っていかないと、サステナブルな関係は築けないと思っています。
秋葉:サステナブルと地域の人とのコミュニケーションを繋げて語れるのはかっこいいですね。竹川さんのお話には人とのコミュニケーションという視点が随所に出てきますが、サステナブルというと物的サービスの話ばかりになりがちです。
竹川:物的なサービスとして、たとえば自然由来の資材に変えるようなことはできるのですが、人と人とのつながりのようなところは、やはりセンターだからできることなのだと思います。
秋葉:大阪のセンターでも同じようなことをしていくのですか。
竹川:マルシェまではできていないのですが、清掃活動や、近くにある小学校の登下校の見守り活動を行っています。その小学校とは少しお話をさせてもらって、端材になったダンボールを提供して工作に使っていただく取り組みもしています。このような余白を楽しむことが、先ほどの「価値」という話につながると考えています。分解したときに、その余白で何ができているか。
秋葉:そこからビームスファンになることもあり得ますね。卒業文集に「ビームスに就職したい」と書く子が出てくるかもしれないですよ。
竹川:私が面接担当だったら、その子が来たらきっと合格にしちゃいますね(笑)。
秋葉:想いを持った人たちが来てくれるのであれば、それでいいような気がします。
竹川:それは物流冥利に尽きるかもしれないですね。洋服やお店での体験が入社につながるのは本当によくある話ですが、物流ではなかなかないので。
秋葉:今後、物流センターがマルチファンクションセンターとして機能していくとなると、EC比率を高めようという戦略なのですか。
竹川:そんなことはなくて、ECも店舗も両方頑張りたいですね。結果としてEC比率が上がることはあっても、EC比率を上げようと意図しているわけではありません。逆に、「EC比率が上がってきてまずいよね」という会話も特にないですね。

秋葉:ビームスさんは比較的店舗の売上が大きいですよね。
竹川:やっぱり店舗はわれわれの主戦場ではあります。
秋葉:店舗で働いている方と接することも価値のひとつです。画面上でポチポチするのと違うのは、僕は、スタッフさんとの会話だと思っています。
竹川:そう言っていただくことが本当に多いので、それをデジタルで体験できるようにすること、ECでも同じ価値を感じていただける設計やサービスをつくることが今後の課題です。
秋葉:ライブコマースもひとつのアイデアです。ライブコマースもある意味で体験なので、そこの体験のさせ方の問題のような気もします。VMD(Visual Merchandising:商品の見せ方、売り場のつくりかたなど、視覚的な演出・販売戦略)として仮想店舗をセンターの中につくって、お店と同じように陳列をする会社もあります。仮想店舗を使ってライブコマースをやったら、没入感があって面白いかもしれません。あとは、ライブコマース限定の商品があるとか。
竹川:物流拠点も利益を生む場所になりたいですね。さまざまなファンクションにおいて、POCを回せたらいいなと思っています。
秋葉:2024年に一般社団法人AIロボット協会が設立されましたが、大和ハウスグループとしても、データを提出して協力していくつもりです。今後、そこで何かご一緒できたらいいですね。先ほどお話があったマルチファンクションの拡張や、サステナブル、アップサイクルの展開など、1年後なのか2年後なのかわかりませんが、またこうした場でアップデートしていただけたら嬉しいです。これからのご活躍を楽しみにしています。